メニュー|事| KG板
2日目|3日目
 会津鉄道 湯野上温泉駅舎内の囲炉裏 |
五月下旬に埼玉発山形行きの旅行へと行ってきました。 出発はやや遅めで、日が出てなお時間が経ってからのこと。前日まで話が固まらないような曖昧な状況が続き、一時は前日出発~最初の休憩地点で車中泊による仮眠、なんて案も出ていましたが、メリットや必要性がないことからなんとかそれは蹴り、朝方の出発に漕ぎ着けたのでした。メンバーは3人、目的という目的もないものの、行くからには何か見てこようくらいの気持ちで一応の見どころの事前調査も少々。 行きはなんということもなくほいほいと進み、大間々~足尾~日光~と順調に進行。龍王峡でトイレ休憩だけして軽く福島県入り。会津田島~塔のへつりを越えてようやくの休憩らしい休憩として湯野上温泉駅に寄り道。それにしても出発からこの方、雨がひどい。気分もひどい。 湯野上温泉駅ではなんと構内に置かれた囲炉裏に火がくべてあり、本来のこの時期であれば暑くて仕方がないだろうところが、この雨のために暖かくて心地よいったら。炭の焼ける臭いがまた好きで、正月などの篝火を思い浮かべます。囲炉裏の脇に座っていたら、「写真をとりますので~」と言われてつい囲炉裏を離れたのですが、撮影者にとってはたんに撮影許可がほしかっただけで、囲炉裏にあたっていた自然体の観光客を含めて撮影がしたかった模様。最初に意図を汲めずに望んだ写真が撮れなかっただろうことにちょっと申し訳ない気持ちがしました。 囲炉裏の他に熊の毛皮や甘酒(100円)があり、甘酒は飲んで置きたかったものの飲まず終い。囲炉裏の炎の動画撮影もしておけばよかった。茅葺の駅舎ということもあって、この旅で巡る歴史探訪の開幕を感じさせます。また、雨ということで手持ちの番傘も早々に出番となり、少しはらしさが出たでしょうか。使い勝手は少々悪い上に破れがありますが、歴史的なものを見てまわることになりそうということであえて持ってきていたのでした。 |
会津若松市に入り、県道64号、325号、374号と変えながら猪苗代湖方面へ。県道64号沿いから、すでに瓦が赤く塗り替えられている鶴ヶ城を望もうとするも、天気の悪さに位置関係の都合もあってからまったく見られず。374号は入り口の松平家墓地の看板が目印であるものの、入り口が一見してホテルの駐車場にすぎないので見落としてしまいそう。事実、4年前には通り過ぎて道を間違えたまま山奥のほうへと行ってしまったし、今回も同じ轍を踏みかけたものの注意をされて誤らずに進行できました。それにしても、墓地とはいえど随分と離れた場所にあるものです。
背あぶり高原キャンプ場を横目に、「ここで一泊もいいね」なんて冗談を飛ばす。猪苗代や若松で一泊して行くには都合いいと思うものの、今回は先へ進むのでそうも行かず。国道294号にぶつかってたいしてたたないうちに原郵便局が出てきたので立ち寄り。国道を進み、福良郵便局の北を行って猪苗代湖畔に到着。写真はキャンプ場付近のもの。雨が降っているための視界不良もあって、一見すると海っぽく見えなくもない。晴れた日でも広さが広さなのでそう見えるかも。雨水によって土砂が流れ込んでいるため、河口付近などが見るからに茶色くなっていました。付近には「領境の松」がありました。少し東に行くと、葦だかが茂った入り江状になっている場所があり、鬼沼という地名がなんだかそれっぽいのでした。

猪苗代湖畔(湖南)
さらに少し南に下った中野郵便局で押印。こちらには旧局舎がまだ残されており、局名もまだ外されていませんでした。自分の好きな木造局舎ではないので旧舎とはいえど比較的新しいのではないかと思いますが、昨今の郵便局の画一化はやはりとてもつまらないです。日本郵便になってからはますます顕著。そういえば、1桁台が端数の切手などが売られていないか各局で聞いて周りもしたのですが、在庫も含めて郵政民営化の前後に発売が終了させられており、なんだか非常に残念です。メモ程度に、現在販売中の切手はこちらになるようです。話は戻って、中野郵便局と旧局舎の間にある小道の脇に市指定文化財の銅鐘の案内棒が立っていましたが、なにがそうなのかさっぱりわからず。後から調べてみたところ、その小道を進んでいった先にある、満福寺にその銅鐘があるようです。

旧中野郵便局
 湖南より湖を東回りに北上。しばらく進むと左手に見えている湖が木々に遮られて見えにくくなったりもします。長いようでそう長くもない道のりを行くと旧猪苗代湖畔駅付近に到着。元々季節限定で開業の臨時駅なのですが、2-3年前くらい前に正式に廃駅にされたようです。駅の向かいにはドライブイン的な場所と駐車場があり、他にもクレープ屋など軽食販売の店がいくつか。廃貨物車両が何両か壁のように置かれていました。 駅のほうはと言えば、元々稼動時期が限られていた上に廃駅となってしまっているので、入り口付近が鬱蒼としています。駅入り口の看板がなければ見落としそう。駅舎はありませんが、改札の駅員用と思われる小さな小屋がありました。ホームはそのままですが、やはり周囲は茂っています。駅こそ使われなくなりましたが、路線はまだ生きているので時々車両の通過はあります。ここでは風雨が一時的に強く、半ば帰れと言われているような感じすらありました。 |
 |
 |
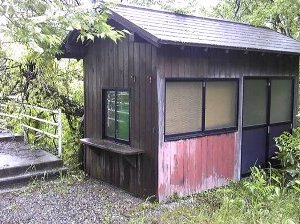 湖畔駅を出てほんの少し北西にある月輪郵便局に寄って風景印を見ると、意匠の一部に鳥居が含まれていました。局員曰く、すぐ近くにある天神社の鳥居だそうで、例に倣って受験シーズンには賑わいを見せるそうです。京都から遥か離れた東北の各地でも天神様の信仰は強く、その高名さは当時から相当なものだったのでしょう。旅行中はあまり気にかけなかったのですが、地図を見ると猪苗代一帯(あるいは会津やさらにその周囲一帯?)では大山祇(オオヤマツミ)神社が非常に多くあります。山の神なだけあってか、こちらも強い信仰をうかがわせます。 猪苗代湖の北側を抜け、野口英世の里郵便局に立ち寄って猪苗代とはおさらば。世界のタバコ販売所IES(E氏との間では無駄に「イエス!」というのが決まりごとになっている)の脇を越えて喜多方方面へ。そういえば、行ったことがない道の駅ばんだいに立ち寄ってみるという案があったけれど、結局近くまで話にまで出しておきながら寄らず仕舞い。かくして、ラーメンの町喜多方へと行き着くのでした。 |
|
喜多方の源来軒というお店で少し遅い昼食として、恒例の喜多方ラーメンを食しました。駐車場はやたらにあるのですが、肝心のお店が見当たらず。ちょっと歩いた所にありましたが表通りにあるわりにはちょっと見落としがち。店内にはTV番組を中心とした各種色紙でいっぱい。上海ラーメンというのが気になったのですが今日はもうお終いと言う事でチャーシューメンを頂きました。麺とスープは良い感じの喜多方ラーメンでしたが、チャーシューは明らかに失敗。普通のラーメンにしておけば良かったです。 さて、喜多方を後にして、毎度立ち寄る道の駅喜多の郷も通り過ぎ、やってきたのは旧日中線熱塩駅を再利用した日中線記念館。日中温泉郵便局の向かいにあって見つけやすいです。 ここではラッセル車と客車が1両ずつ展示保存されており、二重入り口になっている客車のほうは残念ながら車両内部側には鍵がかけられていました。到着時点では管理人さんらしき人が居ましたが、何時の間にやら居なくなっており、鍵は開かず終い。百閒先生の「阿房列車」を読んだせいで、こうしたいかにもなレトロな客車というものが乗ったことも無いくせにひどく懐かしく思えてしまうのでした。ラッセル車のほうは中に入ることが出来ましたが、こちらは感慨深さは特に無し。展示資料。 |
 旧熱塩駅舎内。 木造部分が素晴らしい。  どうみてもターンテーブル。 手動式のように思われる。 |
 展示保存されている客車側入口。 木板の床がいかにも。 |
|
さて、本日のメインディッシュはこちら、朽ちた踏み切り!不謹慎ながらも遺構・遺物好きの血が騒ぐ! ここに来る前にしていた話で「踏み切りや郵便ポストの死骸や抜け殻は実に綺麗だ」などと言ってみたら「抜け殻ってなんだよ」なんて言われたりしていました。まあつまりはこういうもののことなんです。たいていは使途を終えて一同に会して寄り添っているものが見応えがあるものですが、ここの踏み切りのように本来あっただろう位置にそのまま立ち往生している様など素晴らしいことこの上ありません。残念ながら線路跡こそないものの、死してなおのこの存在感。天気に恵まれていなかったものの、この雨に打ちひしがれた様子がむしろ非常に様になっており、こればかりはいい巡り合わせでした。こうなってしまうと九十九の憑きようも無く、死者に対して失礼とは承知でありながらもその抜け殻に魅了されて止みませんでした。「AUTOMATIC ALARM IS OUT OF ORDER」の看板が、ただ「使用中止」と書く以上にまた実に切なさを与えてくれます。あまりに気に入ったので写真は加工なしのサイズでそのまま掲載。とにかく、ここにあってはこの踏み切りが自分にとっての全てとなってしまいました。 踏み切りから続く線路跡地の道を進んで行くと、ターンテーブルにしか見えない遺構がありました。ほんの軽く調べてみると熱塩にはターンテーブルがあっただの、ないだのなんだかてんでんバラバラ。かつては稼動していたものの、なんらかの事由で後年には使えなくなったのでしょうか。すぐ傍らにはターンテーブルから続く位置に車両止めの衝立があり、おそらく鉄道関係施設跡はそこでお仕舞い。衝立のたもとにはスミレと思われる花が静かに咲き栄えていました。 日も傾いてきており、熱塩・日中を後にして福島県を抜けていよいよの山形県入り。 |

| 日の落ちる前に米沢市入り。米沢城址でもある上杉神社の公園に車を停めて、しばし周囲の散策。城址公園と神社境内が入り交じり、非常に良く整備されています。ここから南方面にある林泉寺、急米沢工高へと向かいます。道中にあった商店が良い味を出していましたが、撮影せずに通りすぎたら帰り際にはすでに閉まっていました。あとはタイ料理屋だかなんだかが、その料理とは無関係に気になって話題にしていたり。 |

神社祭殿側から東の参拝路方向を望む。
|
いわゆる国宝である旧米沢工業高校はなかなかの見栄えなのですが、残念ながら玄関口の補修が行われており、壮麗であろう玄関には幕がかけられてしまっていたのでした。明治後期~大正時代の木造建築といえば、こうした正面を中心とした部分の荘厳さが売りなだけに非常に残念。当時この学び舎に通っていた学生などは、当たり前の景色ながらもそれなりに良い心持ちだったのではないでしょうか。事前情報では楽しみの一つだったのですが、この補修と雨の日暮れのためにひどい物足らなさを受けました。 そこからそう離れていない林泉寺には、昨年の大河ドラマで盛り上がった直江兼続夫妻の墓がありますが、観覧には昼の時間に参拝料を払ってとのことでした。すでに時間は過ぎており、今回は表を見ただけでお仕舞い。 |

旧米沢高等工業学校本館。
|
旧米沢工高方面より戻るころにはすでに日は落ちてだいぶ暗く鳴り出しています。行き帰りと上杉伯爵邸の前を通りましたが、通る度に中を羨んだりしていました。こんなところで一度食事をしてみたいものです。 |

最後に米沢城址の朱塗りの橋を一枚。
|
すっかり夜になったところで最後の出発、南陽市は道の駅高畠近辺へ向かいます。途中でスーパー・ヤマザワに寄って少々の食料追加。このあたりでは、キムラとヤマザワが二大スーパーとして幅を利かせているようですが、見た感じヤマザワのほうが大量仕入れ、大量販売を行っていて勢いがあるようでした。 できればキャンプサイトに寄りたいものの、止む無く近隣にテントを設営しての一泊。設営から翌朝まで、うまいこと雨が止んでいてくれて助かりました。ちょっとお行儀が悪いですが、世の中はどんどん規制が厳しくなっていくものと痛感もします。 1日目終了。2日目へ続く。 2日目|3日目 メニュー|事| KG板 |